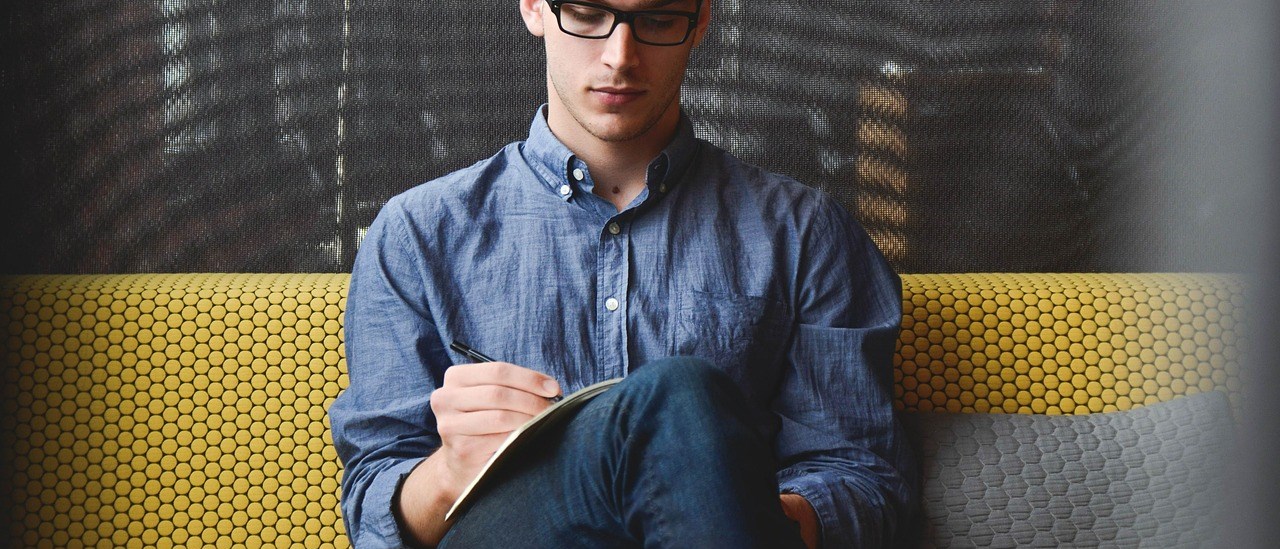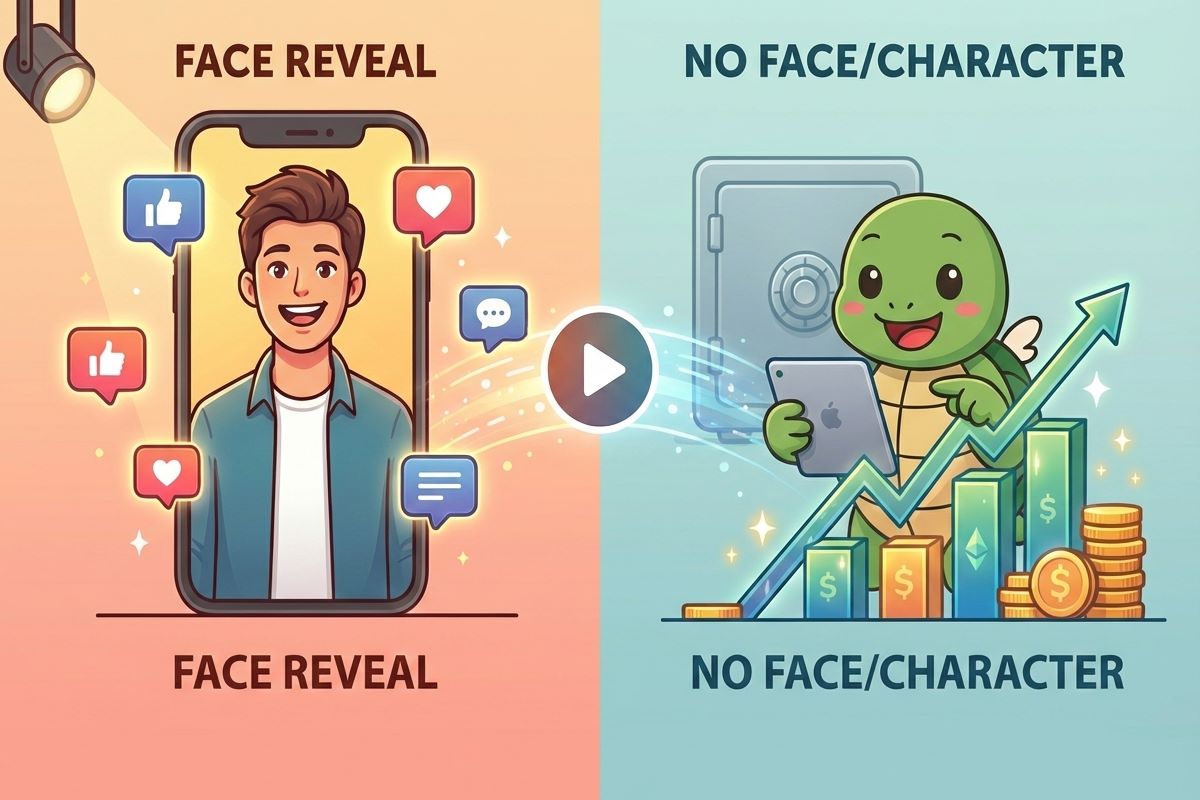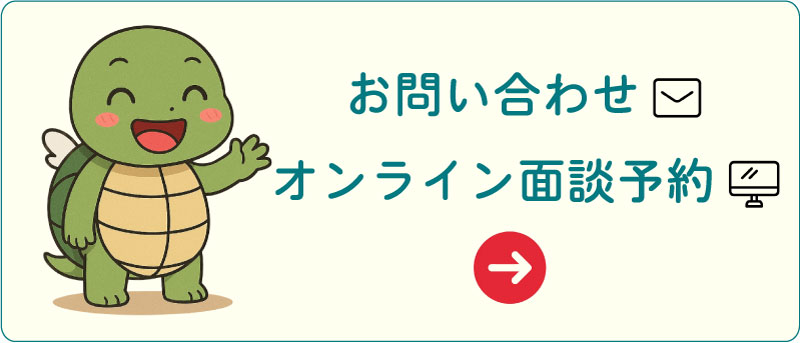企業の広報活動において、ショート動画の活用が注目されています。特にTikTok、YouTube Shorts、Instagram Reelsといった縦型ショート動画フォーマットは、従来のWebマーケティングとは異なるアルゴリズムやユーザー行動に基づいた新たな訴求手段として注目を集めています。
かつて企業の広報活動といえば、テレビCM、新聞・雑誌広告、あるいはプレスリリースといった、マスメディア中心の施策が主流でした。しかし、情報流通の重心がスマートフォンとSNSへと完全に移行した現在、広報の現場は劇的な変化を遂げています。その中でも特に注目されているのが、TikTok、YouTube Shorts、Instagram Reelsといった縦型ショート動画を活用したプロモーションです。
これらのプラットフォームは、単なる若年層向けのエンタメではありません。企業のブランド認知、商品・サービス訴求、採用広報、ブランディッドコンテンツなど、さまざまな広報目的において、再生回数を起点とした広がりを狙える手段となっています。ただし、闇雲に動画を投稿しても視聴される時代ではありません。再生回数を戦略的に伸ばすには、アルゴリズムの理解、ユーザーインサイトの把握、明確な目的設計、そして継続的な効果測定が不可欠です。
企業PRの文脈においてショート動画を活用する際、どのような視点と戦略で「再生される動画」を作るべきかを、主要プラットフォームごとの特徴や具体的な工夫とともに、実践的に解説していきます。再生回数の最大化を目的とした企業PR視点でのショート動画戦略について、各プラットフォームの特徴や再生数を伸ばすための方法を、広報担当者の目線で詳しくご紹介していきます。
なぜ今、ショート動画が企業広報に重要なのか
SNSの利用形態が変化し、「テキスト→静止画→動画→ショート動画」と進化してきた流れの中で、縦型ショート動画は圧倒的な消費速度と拡散力を持つメディアとして確立されました。スマートフォンでの閲覧に最適化されていることから、ユーザーが日常的に視聴する機会が多く、エンタメ性・広告性・教育性のいずれにも対応可能な柔軟性を備えています。
さらに、プラットフォーム側もショート動画の視聴時間を伸ばすことで広告収益を増やせるため、アルゴリズムは積極的に拡散するよう設計されています。これは、フォロワー数やブランド認知度に左右されず、純粋に動画の完成度や反応率によって拡散されるチャンスがあることを意味します。
つまり、スタートアップ企業から大手まで、等しく再生回数を獲得できる土壌が整っており、企業広報にとっては「リスクが低くリターンが大きい」新たな選択肢となっています。.
再生回数を左右する本質的な要素
「バズる動画を作りたい」という要望は非常に多く聞かれますが、実際には“バズ”よりも“視聴完了”が重要です。ショート動画のアルゴリズムは、どのプラットフォームでも次のような要素を重視しています。視聴完了率(Completion Rate) 視聴維持率(Retention) 滞在時間(Watch Time) シェア・コメントなどのエンゲージメント 視聴者行動(プロフィール遷移、外部リンクタップ等)
つまり、「最後まで見られる動画」「視聴後に反応を生む動画」こそが、再生回数を自然に伸ばせる構造になっています。そのためには、編集の巧みさ以上に、伝えたいメッセージをいかに短時間で魅力的に提示できるかが鍵になります。
ショート動画の再生回数を効率的に伸ばし、自社のブランディングやサービス認知を拡大するためには、単なる「動画投稿」では不十分です。企業の広報担当者が押さえるべきは、アルゴリズムの特性を理解したうえでの動画構成、トレンド性と独自性のバランス、最適なフォーマット選定、そして一貫した効果測定です。TikTok・YouTube・Instagramそれぞれにおける再生回数向上の要因には共通する部分もありますが、プラットフォームごとの特性を正しく把握し、運用を最適化することが再生回数の安定的な増加に寄与します。
TikTok:初動2秒がすべてを決める
TikTokは再生回数が初速で決まる典型的なプラットフォームです。投稿直後に表示されたユーザーの反応をもとに、拡散対象かどうかが判断されます。特に重要なのは「視聴開始2秒での離脱率」と「完全視聴率」であり、この2点が悪ければフォロワーが多くても再生数は伸びません。
企業がTikTokで再生回数を狙うには、「2~3秒以内に答えを出す」動画構成が基本になります。たとえば、「〇〇の裏側に密着」「話題の××を試してみた」など、冒頭に強いフックを置き、続きが気になる構成にする必要があります。
UGCとの連動
また、TikTokではUGCとの連動が非常に有効です。企業が主導するハッシュタグチャレンジ、音源提供、参加型コンテンツなどを通じて視聴者の能動的関与を促すことで、単独投稿では届かないリーチを獲得できます。社員の登場や製品の使い方をユーザーと一緒に作る構成も効果的です。
TikTokは、アルゴリズム主導でコンテンツの拡散が行われるプラットフォームであるため、初動のインプレッション率とエンゲージメントが極めて重要になります。
UGCを味方につけるTikTok・Instagramの集客・採用戦略
「滞在時間(Watch Time)」と「完全視聴率(Completion Rate)」
投稿直後の「滞在時間(Watch Time)」と「完全視聴率(Completion Rate)」が高ければ、フォロワー数に関係なく爆発的に再生数が伸びる可能性があります。
したがって、企業が広報的意図を持ってTikTokを運用する際には、開始3秒以内に視覚的インパクトとメッセージを提示する構成が再生率を左右します。
また、UGC(User Generated Content)と掛け合わせて参加型の企画に落とし込むことで、視聴者による能動的な拡散が期待できます。企業ロゴや商品が自然に映り込む構成にすることで、過剰な宣伝とならずに認知の浸透を図ることが可能です。
YouTube Shorts:チャンネル評価との連動を意識する
YouTube ShortsはTikTokよりもチャンネルの「信頼スコア」の影響を受けやすい仕様です。単発で再生数が出るケースもありますが、過去の投稿実績や本編動画の評価、コメント数、登録者との関係性がアルゴリズムに反映されるため、継続的な運用が必要です。
特に重要なのは、タイトル・説明文・ハッシュタグにおける「検索性の高いキーワード設定」です。YouTubeはSEOとの親和性が高く、企業にとってはブランド名・商品名だけでなく、業界キーワードや利用シーンを組み込むことで中長期的に動画が見られやすくなります。
また、Shortsにおいても「先に価値提示、後からブランド提示」の順番が有効です。冒頭で視聴者にとっての“学び”や“驚き”を提供し、その延長線上で企業名や商品が登場する構成にすることで、視聴維持率が上がり、結果として再生回数の最大化に繋がります。
YouTube Shortsにおいては、レコメンドエンジンがYouTube本体と連動しており、既存のチャンネル評価や投稿履歴が影響を及ぼします。
チャンネル全体のエンゲージメント率(ER:Engagement Rate)
再生回数を伸ばすためには、単体のショート動画の完成度だけでなく、過去の動画との整合性や、チャンネル全体のエンゲージメント率(ER:Engagement Rate)を意識した運用が求められます。
また、YouTubeはSEOのロジックが強く反映されるため、タイトル・説明文・ハッシュタグにおいて検索性の高いキーワードを適切に選定する必要があります。企業のプロモーション目的であっても、ブランディング要素や宣伝色が強すぎるとユーザー離脱を招き、視聴維持率が下がる傾向があります。そのため、ショート動画では「先に価値を提示し、後からブランド要素を重ねる」という構成が有効です。
Instagram Reels 世界観と審美性を突き詰める
Instagram Reelsの特徴は、アルゴリズムの独自性と、ユーザーの「審美眼の高さ」です。Reelsはフォロー外のユーザーに届く主要機能である一方、インスタグラムというビジュアル特化型SNSの性質上、動画の画質・色調・構成・BGMに対する期待が他のプラットフォームよりも高い傾向があります。
企業PRにおいては、ビジュアル・世界観の統一、キャプションのトンマナ、音楽の使い方など、総合的なブランド演出力が求められます。また、動画内に表示するテキストも「タイミング」「場所」「量」によって印象が大きく変わるため、UIデザイン的な発想が必要になります。
Instagramのアルゴリズムは“保存数”や“プロフィール遷移数”も重視しており、ユーザーに「もう一度見たい」と思わせるような構成や、「この人誰?」と気になるナレーション構成などが再生数に直結します。
Instagram Reelsでは、ビジュアルのクオリティとトレンド適応力が重要となります。
Instagramのユーザー層は視覚的審美性への期待値が高いため、撮影・編集段階でのカラーグレーディングやカメラアングル、BGMの選定などにおいて高い品質を維持する必要があります。また、Instagramではフォロー外ユーザーへのリーチをReelsが担っているため、キャプションの工夫だけでなく、動画内テキストの配置位置や表示タイミングといった視覚的UI演出にも注意を払う必要があります。
再生完了率やリテンション率、動画クリック率(CTR:Click Through Rate)、タップアクション
さらに、ショート動画における再生数の指標は単なる「視聴された回数」だけでは評価しきれません。再生完了率やリテンション率、動画クリック率(CTR:Click Through Rate)、タップアクション(例えばプロフィール遷移やリンククリック)など、多面的な指標に基づいて改善点を明確にし、制作方針に反映させていく必要があります。
ショート動画は一過性のトレンドに依存する部分が多く、投稿の鮮度も重要な要素です。そのため、投稿スケジュールを戦略的に設計し、週単位または月単位で「反応が取れるテーマ」を検証していくことが継続的な改善に繋がります。特に企業の場合、キャンペーンや季節商戦と連動させて投稿することで、動画のバズ効果と実売への結び付きを高めることができます。また、インフルエンサーとのタイアップや、既存フォロワーとの協業によって、動画の到達範囲を拡大させる戦術も有効です。
近年では、各SNSが提供する「動画広告メニュー」との連動も注目されています。TikTokではSpark Ads、Instagramではブースト投稿、YouTubeではVideo Reach Campaignsなどが用意されており、自然流入だけでは届かない層への接触を可能にします。これらの広告配信においても、オーガニックなショート動画の反応率が高い素材であればあるほど、費用対効果が高まる傾向にあります。
ショート動画の運用はクリエイティブの自由度が高い反面、配信側の意図が伝わらなければ結果にはつながりません。再生回数を増やすという目標においても、単に数字を追うのではなく、その背後にある「誰にどんな印象を与えたいのか」「何を知ってもらい、どう行動してもらいたいのか」といった明確な目的設計が不可欠です。企業PRにおいては、短い時間の中に込められたメッセージ性と、それを裏付ける戦略設計こそが再生回数の最大化を実現する鍵となります。
今後も各SNSプラットフォームのアルゴリズムやユーザー行動は変化していきますが、広報担当者がその変化を定点的に観察し、柔軟に動画設計をチューニングすることで、継続的な成果につなげることが可能です。
トレンドと独自性のバランス
再生回数を獲得するには、トレンドに乗ることも必要ですが、単なる模倣では埋もれてしまいます。企業が行うべきは「トレンドの型に、独自の切り口を掛け合わせる」ことです。
たとえば、「話題の音源」や「人気の構成」を踏襲しつつ、自社の商品や業界特有のあるあるネタを織り交ぜるだけで、視聴者にとって新鮮に映ります。また、毎週1つ「トレンド分析会議」を設け、業界特化型のフォーマットを定期的に開発していくことも、運用面では有効です。
再生数だけで成功は測れない 多面的指標と目的の再確認
広報の現場では、再生回数だけに注目してしまいがちですが、それだけでPR効果を評価するのは危険です。特に企業アカウントの場合は、「再生された結果、どんな行動変容が起きたのか」に着目する必要があります。
以下のような複合的な指標を継続的に観察し、PDCA的ではない「意味のある改善」に取り組むべきです。再生完了率 CTR(リンククリック率) プロフィール遷移率 保存数/シェア数 他動画・サイトへの遷移行動
これらは、社内プレゼン資料やレポートにも活用でき、広報活動のKPI管理にも資する情報となります。
広報担当者が担うべき役割と変化対応
アルゴリズムは変わります。ユーザーの嗜好も日々変化します。その中で企業の広報担当者に求められるのは「一貫性ある目的」と「柔軟な設計」です。
たとえば、「採用目的」「商品認知」「市場啓蒙」など、目的が明確であれば、表現や構成は大胆に変えても構いません。逆に目的が曖昧なまま動画を量産すれば、どれだけ再生回数が増えても企業ブランドへの定着には繋がりません。
広報とは、「誰に、何を、どう伝えるか」の設計業務です。ショート動画が主戦場になった今、その設計の質が問われているのです。
再生回数の背後にある動画企画が企業価値を左右する
ショート動画の再生回数は、もはや単なる数字ではありません。そこには、ユーザーが反応した「構成力」、シェアしたくなった「納得性」、保存した「記憶価値」が含まれており、動画ごとのメッセージと設計の精度が数字に現れています。
だからこそ、企業がこの領域で勝ち抜くには、映像制作のテクニック以上に、「なぜ再生されるのか」を深く理解し、「どう伝えるのか」に戦略を持つことが求められます。
再生回数を最大化するとは、広報の未来に真剣に向き合うことにほかなりません。変化を先取りし、自社に最適な「短尺型・伝達力強化メディア」としてのショート動画を活かすことが、これからの企業広報の標準となるでしょう。
企業が自力で取り組んだ場合のよくある失敗例
ショート動画の運用は一見手軽に始められるように見えるため、外部の支援を受けずに自力で始める企業も少なくありません。しかし、そうしたケースでは再生回数が伸びず、かえって「動画施策は効果がない」という誤った結論に至ることもあります。以下に、企業が自力でショート動画に取り組んだ際によく見られる失敗パターンをいくつか挙げ、それぞれの背景と注意点を考察します。
よくあるのが、既存の広告動画や社内イベント映像などをそのままショート動画化してしまうケースです。テレビCMや会社紹介PVを短縮するだけでは、視聴者の興味を引くことは難しく、アルゴリズムによる推薦にも乗りづらくなります。
特にTikTokやInstagram Reelsでは、ネイティブな演出やカジュアルなテンポが求められるため、過度に編集された企業色の強い動画は「広告」として認識され、即座にスキップされる傾向があります。社内で過去に制作した動画を流用することはコスト面では効率的に見えるかもしれませんが、ショート動画に適した文脈や構成を無視した制作は結果につながらないことがよくあります。
SNS運用・動画配信で成果の出やすい企業の特徴とSNS運用代行が向いている業種
企画の不足とユーザー動向の調査不足
次に多いのが、発信目的が曖昧なまま投稿を続けてしまうパターンです。ブランディングをしたいのか、商品認知を広げたいのか、採用広報なのかといった目的が曖昧なまま、「とりあえず流行っているからやってみよう」という姿勢で投稿している企業アカウントも少なくありません。このような場合、ターゲットが定まっていないためメッセージがぶれ、結果として誰にも刺さらないコンテンツになってしまいます。目的を明確にしないままトレンドに乗ろうとしても、アルゴリズムと視聴者の両方に無視されてしまうのが現実です。
さらに見逃されがちなのが、企業の広報部門が「伝えたいこと」を中心に動画を構成してしまい、「ユーザーが知りたいこと」や「共感する要素」を軽視してしまうという点です。
商品説明や企業理念の押し付けは、ショート動画においては逆効果になることがあります。
視聴者はまず楽しさや意外性、共感といった感情的な価値を求めており、情報はその延長線上で受け取るものです。このような視点のズレに気づかず、自社目線で企画を進めてしまうことが、動画の伸び悩みにつながる典型的な失敗といえるでしょう。
投稿頻度
また、投稿頻度のバラつきも失敗要因の一つです。自社で完結しようとすると、担当者の業務負荷が高まり、投稿が不定期になったり、1ヶ月間空いてしまったりすることがあります。ショート動画においては「継続性」が非常に重要であり、アルゴリズムもアクティブなアカウントを優遇する傾向があります。最初の数本だけ投稿して更新が止まってしまうと、せっかくの初動で得られた少量のインプレッションさえも失われ、アカウント自体の評価が下がってしまう可能性があります。
分析と改善の重要性
一方で、視聴分析を怠ることも深刻な問題です。せっかく動画を投稿していても、再生回数や視聴完了率、フォロー転換率などを継続的に分析しないまま運用していると、改善のヒントを見逃してしまいます。たとえば、最初の3秒間で視聴者が離脱しているのであれば、冒頭の構成に問題があると判断できます。しかし、データに基づかない感覚的な投稿を繰り返していては、改善もままなりません。自力で取り組む際には、最低限の指標モニタリング体制を整えることが不可欠です。
全社的な動画理解の不足も見逃せません。自社制作で完結させようとすると、動画の重要性や役割について理解が浸透していない部門との連携がうまくいかず、企画そのものが社内調整で止まってしまうケースもあります。特にBtoB企業では、製品部門や法務部門との調整に時間がかかり、結果的に投稿機会を逸することもあります。動画施策はスピードと柔軟性が命であるため、社内理解を得ずに個人プレーで進めてしまうと、継続的な運用が難しくなります。
これらの失敗例に共通して言えるのは、ショート動画を「特別な何か」として捉えず、マーケティング活動の一環として位置づけられていないことです。再生数を伸ばし、PR効果を最大化するには、専門的な知見や外部支援を取り入れながら、継続的にPDCAを回していく(※表現変更可能)姿勢が求められます。
自力運用の限界を正しく認識し、戦略的な体制を整えることが、企業のショート動画成功への第一歩となります。
バズるTikTok動画の秘密 再生回数を爆増させる動画構成とバズいらずのSNS運用